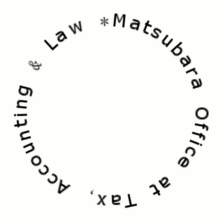 相 談 例
相 談 例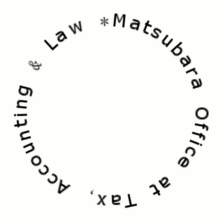 相 談 例
相 談 例 |
| ◆父(母)が亡くなったら何をすればよいのですか ・死亡を知った日から7日以内に市区役所・町村役場に死亡届を死亡診断書を添えて提出します。市営葬等の場合は葬儀の前に提出しなければなりません。 ・喪主は誰がやるか、墓は誰が守るかという決まりはありません。それぞれの地方の慣習に従い相続人が話し合って決めます。 喪主になった方は何をどうしたらいいのかお困りと思います。故人の信仰する宗教に従い葬儀を行いますが、そのようなとき、酒井美意子監修・すぐに役立つ冠婚葬祭心得集 (家の光協会,1994初版)がたいへん参考になります。 ・葬式の前後で葬儀費用や法会、「お別れ会」などの開催に多額の支出が必要になります。故人の預金口座が閉鎖されてしまった場合は、銀行所定の払戻し請求書に相続人全員の実印を押し印鑑証明書を添付したものを銀行に提出しないと引き出すことができません。なお遺産分割協議書を提示して払い戻すことも可能です。 |
| ◆遺言書や分割協議にはどのように対処したらいいのでしょうか ・亡くなった日からしばらくしたら(仏教なら四十九日の法要を終えた頃)、相続人の間で遺言書の有無を確認し(公正証書遺言なら、平成元年以後に作成されたものに限り全国どの公証人役場でも遺言検索をすることができます)、遺言書がなければ相続人同士で遺産分割協議を開始することになります。 ・公正証書遺言以外の遺言書が発見されたら、開封せず、家庭裁判所に持ってゆき、検認手続を受ける必要があります。 ・相続人全員が合意すれば、家裁に申し立てて遺言書と異なる遺産分割をすることができます。 ・遺産分割協議に当っては、故人の財産の分割の他、老いた配偶者の生活保障や墓を誰が守るかを考慮に入れる必要があります。遺産分割協議が成立しない場合に家庭裁判所の調停に持ち込まれることがありますが、そのようなときには民法に定める法定相続分による分割を勧められることが多いようです。 |
| ◆相続税はどのように計算されるのですか ・一億円する百坪の土地にはいくらの相続税がかかるかという質問は無意味です。 ・故人が所有していた財産(非課税とされるものを除き、生前3年内の贈与額を加算し、相続税の基礎控除額※を控除した後の金額)を法定相続人が法定相続分に応じて相続したものとみなして、まず相続税の総額を計算します。 相続人個々の相続税額は、相続税の総額を各相続人が取得した財産の価額により按分して求めます。 ・なお名義預金や名義株は故人によって管理されていたような実態があれば、相続財産とされてしまうので注意しましょう。また財産の秘匿を指摘され、修正申告に応じても配偶者の税額軽減を適用できなくなったのはご周知の通りです。 ※相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
| ◆相続にあたって気をつけることはありますか また、相続税の節税は? ・相続対策とは、①「争族」を避けるための遺産分割の問題を把握し、遺言書の作成の可否を検討すること、②①に伴って生ずる相続税(と贈与税)の負担を最小限にすること、③相続税が生ずる場合に納税資金を事前に準備すること、の三つです。 ・事前対策と事後対策がありますが、税金面で言うと、相続が起きた後でもあきらめる必要はなく、事後であっても対策はいくらでもあります。分割の態様により相続税額が変わってきますので。 ・納税資金対策としては、納税額に比例させて現金その他の金融資産を相続させるのはもちろんです。 また、保険会社から支払われる生命保険金を活用するほか、相続した財産の中に不動産や(故人が主宰していた)同族会社の株式があれば、会社に買い取ってもらう方法もあります。 |
| ◆相続税の事前対策にはどのようなものがありますか ・相続の対象となる財産を減らすこと。そのためには特例を活用した生前贈与を積極的に行います。例えば贈与税の配偶者控除など。なお相続税精算課税制度の活用による節税効果にはいまいちです。 ・現金資産や流動性資産は名目金額に相続税がかかるので、不動産の収益物件を購入したり生命保険に加入したりして資産を組み替え、あるいは同族会社を設立して資産を法人に譲渡(株式を通した間接所有)することなどにより、相続財産の評価額をあらかじめ引き下げます。 |
| ◆相続税の税務調査にはどのように対処したらいいのでしょうか ・相続事案の税務調査の多くは9月から12月までの間に行われます。 ・故人の履歴、職業、趣味、病歴や入院期間に関する聞き取りや現物確認などにより、特に預貯金の申告が適正に行われているかを調査されます。遡るのは5年(大口は10年)位で、大きな金額の出入りをチェックされ、申告外の資産や贈与を把握されます。 ・実質的に故人が管理・費消していた配偶者、子、孫などの名義による預金や有価証券は相続財産とされるため、申告が必要ですので注意しましょう。 ・調査官は実績を上げるため、時として予見を持って修正申告を迫ったり、質問検査権の必要限度を超えた調査をすることがあります。この場合には、納税者の代理人として厳正に対処させてもらうことになります。 |

|
| ◆事業経営はどうしたら成功できるのでしょうか ・「自分自身が納得できる最高の商品を創るために仕事を毎日こなしていくこと。」これが最高の経営であり、経営者の仕事です。 ・経営で一番大切なのは資本です。起業するのにお金が足りないときは、どんなことをしてでもまずタネ銭を貯める。廃品回収業でもビル清掃でもドブさらいでもコンビニの店員でもよいのです。どんなに親切な隣人でも「金を貸してくれ」と言えば逃げていきます。 ・同じ仕事能力でも資本があるのとないのとでは大違いです。金を借りるのは、返す時に税金を考えると、返済金の2倍儲けなければなりません。返済の原資は利益しかないという簡単なことが多くの経営者にはわかっていません。 ・起業するときには人に相談しないほうがベターです。経営で成功している人がその秘訣を只で教えるわけありませんし、そのようなことを他人に相談するようでは経営者として失格です。 ・ではどうしたら成功できるのか。それは始める商売についてどれだけの知識を持っているかという一点にかかっています。商売とはリスクです。楽して儲けるとか、仕事は楽しくなければと思っているような人は商売に向きません。また、人の後ろについていくような人も。人の裏を掻くようなことをしないと利益は挙げられません。 ※詳しくは、成功の秘訣をお読み下さい。 |
| ◆法人成りするとどのようなメリットがありますか ・事業をするにも個人に比べ対外的な信用力が増加し、資金調達の面でも有利になります。 ・家計からの分離により法人としての事業の経営成績、損益構造が明確になります。また、経営に計画性が出てきて事業拡大に弾みがつきます。 ・株式会社、合同会社に法人成りすれば、株主(出資者)は有限責任性を享受できます。 ・法人に対する税金は比例税率により課されるので、一般的には個人に対する税金よりも軽減され、経営体力を温存できます。 ・法人に対する現物出資や財産引受により個人財産を法人に移転しておけば、株式による所有となり、一般的には相続税は軽減されます。 |
| ◆会社の設立をしたいのですが ・会社法の改正により、最低資本金制が廃止されて1円起業が可能になり、定款の自由な設計や一人株式会社が認められるようになりました。とは言いましても開業資金としては、対外的信用を得るためには旧有限会社の出資金である300万程度は必要でしょう。 ・会社の設立に当たっては、設立登記のほか本社の賃借、什器備品の取り揃え、社会保険への加入、各官公署への諸届出など起業者にとっては煩わしく思われることが少なくありません。 当事務所は、ワンストップ・オフィスとしてこの部門の各専門家と連携しお客様のご要望に沿った会社作りを心がけています。 |
| ◆資金的に余裕がないので自分で経理処理をやりたいのですが ・最近はパソコンが普及しウェブ上からあらゆる情報を入手することが可能になり、ご自分でソフトを買って経理処理をされている方が増加してきております。このような方のため、ご要望に応じ、資金のご負担を最小限にするよう顧問契約後一定期間フリーまたは割引にて報酬規程を設定しておりますので、お気軽にコンタクト下さい。 ・当事務所は株式会社弥生の弥生PAP会員となっておりますので、「弥生会計」、「弥生販売」、「弥生給与」、「やよい青色申告」について、その導入や運用などについては、フルサポートを行っております。 ・申告のみあるいは「年一」のお客様についても、報酬規程にて考慮しております。その際税務上のリスクをご理解いただき、帳簿や伝票を網羅的に拝見し、是正すべき点を指摘させていただくこともありますので、ご留意下さい。 ※報酬規程や具体的なお見積りについては「お問合せフォーム」にてご請求下さい。 |
| ◆所得税・法人税の税務調査にはどのように対処したらいいのでしょうか ・会社や個人事業に対して行われる調査は基本的には任意調査です。仕事に支障が生ずるような場合は日程を延期してもらうこともできます。また業務に関係のない書類の閲覧等は納税者が同意しない限り、拒むことができます。 ・調査に当たって事前に十分に帳簿や証憑を確認する、調査官を招じ入れる場所の検討、想定問答をもとに予行演習するなど、周到に準備することが、何年かに1回の緊張の日々を乗り切るための秘訣です。 ・受け易い会社は、例えば売上が急激に伸びている会社、収益の伸びに比し利益の計上がマッチしていない会社、法人成りした会社、ワンマン経営の会社、現金預金の異常に多い会社、脱税志向の強い会社などです。 ・多額の追徴金や加算金で資金的に苦しくならないためにも、日々の取引の適切な記帳や税務処理、領収書・請求書などの会計証憑の保存・管理をきちんとしておくことが必要です。 ・調査官は実績を上げるため、時として予見を持って修正申告を迫ったり、質問検査権の必要限度を超えた調査をすることがあります。この場合には、納税者の代理人として税理士が厳正に対処させてもらうことになります。 |

|
| ◆差し引かれる社会保険料や源泉所得税について教えてください ・会社から給料を支給されるときにもらう給与明細には、基本給や諸手当の金額、天引きされる社会保険(健康保険、40歳以上の方は介護保険、厚生年金保険)や雇用保険の保険料、源泉所得税、特別徴収の住民税の額が記載されています。 ・まず、残業手当、職務手当、能力手当、家族手当、通勤手当などの諸手当は、すべて社会保険適用上の報酬・雇用保険の賃金に含まれ、保険料の計算基礎にされます(通勤手当の非課税部分を含みます)。退職金は報酬・賃金に含まれませんが、賞与は含まれます。 ・社会保険の保険料は、標準報酬月額を基礎に前月支給給与について、雇用保険の保険料は、当月支給給与の額に料率を乗じて算定されています。平成15年4月より施行された総報酬制により賞与にも毎月の給料と同一の保険料率が適用されることになりました。 ・所得税の課税対象になるのは、通勤手当の非課税額を除いた基本給と諸手当の合計額から上記保険料を控除した後の金額です。この所得税は概算額ですので、原則として年末調整により12月に支給される給与の額で過不足が調整されます。また、住民税は、普通徴収を選択する場合を除き、前年分の所得について計算された住民税を当年6月から翌年5月までの給料から天引きして徴収します。 |
| ◆扶養に入るときどのようにすれば税金が安くなりますか ・「扶養に入る」とは俗語ですが、1.健康保険の被扶養者又は厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者になること、2.所得税の計算上、控除対象配偶者又は扶養親族になることを意味することが多いようです。 ・上記1.の健康保険の被扶養者(国民年金の第3号被保険者)となるには、主として被保険者によって生計を維持されていることが必要です。 原則として、被扶養者の年間収入(公的年金・雇用保険給付・非課税通勤交通費などすべての収入を含む)が130万円(60歳以上の老年者等の場合180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合には、被保険者によって生計を維持されているものとされます(同一世帯の場合)。被扶養者には健康保険や厚生年金保険の保険料の納付義務はありません。 ・配偶者が失職したこと等により被用者保険から脱退することになったときや被扶養者に該当しないこととなったときは、第1号被保険者として国民年金に加入することになり、市区町村の窓口での手続が必要です。 ・上記2.の所得税の控除対象配偶者又は扶養親族とは、居住者と生計を一にする配偶者又は親族でその年分の合計所得金額が38万円以下であるものをいいます。無収入の人あるいは給与収入とすれば年間収入が103万円以下である人が該当します。 ・家計のことを考えるなら、もし可能なら年収を103万円以下(所得税の軽減)又は130万円未満(保険料の節約)に調整します。年収が103万円(130万円)を超えても(以上になっても)、141万円未満なら配偶者特別控除を適用できます。 でも共稼ぎならお二人の収入が多いに越したことはありません。家計(お二人の収入合計)の手取りが最大になるように研究することをお奨めします。 |
| ◆リストラされそうなときどのように対処したらいいのでしょうか ・会社は従業員を解雇できないと思い違いしていないでしょうか。残念ながら使用者・労働者いずれの側からも雇用契約の解消をすることができることになっています(民法627条)。ただし、労働基準法では、合理的な理由がなく社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権の濫用として無効であると言っています(同法18条の2)。解雇権の濫用とされる判例が蓄積し、平成15年の労働基準法の改正で18条の2が設けられました。 ・懸命な経営者なら解雇通知というような冒険はせず、明らかに解雇事由になる場合を除き、退職願の提出を求めるのが通常です。それが意に染まないときは決して退職願は出さないことです。 ・実績が上げられないとか勤務態度が悪いというだけでは解雇されません。では「明日から来なくてよい」と宣告された場合はどうするのか。自分には落ち度がなく解雇を言い渡される筋合はないと思ったら、二つの方法があります。 ①解雇を認めて給料1か月分の解雇予告手当を請求します(労働基準法20条)。 ②書面で解雇通知が来たら、退職の意思がないこと、これからも給料を支払ってほしい旨を弁護士に内容証明郵便で伝えてもらいます。 ・上記②の効果は強力ですので、退職が意に沿わないときは「弁護士に相談してみる」と言えば解雇を撤回する場合もありえましょう。そうでない場合は、裁判が片付くまでその期間の給料などが保証されることもあります。 ただし、勝訴後復職してみても職場での居心地の悪さが拭いきれません。人生は長いですから、新しい道を模索してみるのが懸命な選択となる場合があります。 ・試用期間満了前の本採用の見合わせという手段が取られることがあります。これも解雇に含まれますが、採用から14日以内なら解雇予告手当を払わなくて済むこと、試用期間中の解雇が比較的認められ易く、しばしば行われるので注意しましょう。 ・解雇が無効と会社に告げたのに給料が払われなかった場合、平成18年から実施されている労働審判手続の申立という選択肢があります。この手続は調停によって始まりますが、調停が成立しない場合は裁判所により労働審判が行われます。弁護士に依頼する費用がないときは本人でもできるので利用してみてはいかがでしょうか。 |
| ◆土日起業をしたいのですが ・勤めている会社の存続自体も絶対ではありません。家電のパイオニア以来、会社の解雇権が認知されつつあります。そのような状況で従業員が自分の生活を防衛しようとするのは当然です。かと言って、簡単に独立できるほど世間は甘くありません。大多数の人は会社にしがみつくしかないのです。 ・企業の8割が副業を禁じていますが、サラリーマンのうち3割の人は副業経験があると言われています。ただし、週末に副業しても稼ぎは僅かですし、「勤め人」という受身の身分であることに変わりありません。副業と起業は180度違うのです。 ・ところで、起業に向く性格とは、「感情量」の大きさであるとある脳科学者は語っています。感情量の大きい人とは、①自分が絶対正しいという傲慢さ②好奇心が強くしかも移り気③徹底的なこだわり④負けん気が強く妥協しない⑤人の好き嫌いが激しい、人見知り⑥失敗すると落ち込み、長く引き擦る。意外でしょう。短所と思っていた自分の性格を長所に転ずるよい機会です。 ・次に、起業するための適性とは、①愛想がよいこと②ウソをつかないこと③勤勉であること④(時代に)敏感であること⑤「希少性」のあるアイデア(商品)を持っていること、です。このうち一番大切なのは⑤です。 ・起業には元手が必要です。それなら資金のない人は、勤めながら給料によって原資を稼げばよいのです。簡単に会社をやめてしまってはいけません。その意味では会社は貴重な出資者です。と同時に、起業に失敗して元々だし、リスクを回避できます。企業はいつでも独り立ちできる有能なサラリーマンを求めているのですから、起業がバレたらすぐクビにするような会社なら、元々籍を置く価値のない会社でしょう。 ・そこで、「週末起業」なのです。給料をもらいながら、「希少性」のあるビジネスを考えてみてください。ネット上で「今ならどんなビジネスが儲かりますか」と聞くような人は起業に向きません。それはネット上にも、雑誌にも本にも新聞にも書いてありません。全ては自分自身がたよりです。町に出て、身銭を切って現地に出かけ、人と話をし、何かをやってみるのです。 |
| ◆確定申告はどのようなときにするのですか ・給与所得を得ている人の大部分は、年末調整により所得税が精算されますので申告をする必要はありません。ただし、その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人、給与を2か所以上から受けていて年末調整をされていない給与所得のある人等は、原則として申告が必要です。 ・申告義務のない人でも、雑損控除、医療費控除、寄付金控除や居住開始年分の住宅取得等特別控除を受ける人は、申告をして所得税額の還付を受けられる場合があります。 ・不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得又は公的年金等に係る雑所得を得ている人は、原則として申告義務があります。 ・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人は申告義務があります。 ・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける人は、上記に当てはまらない場合であっても申告が必要です。 |
 |
〒160-0003 東京都新宿区本塩町21番地 松原ビル4階 税理士松原 順事務所 Tel:(03)3359-2357/Fax:(03)3359-8042 Email: attorney@rondo.plala.or.jp ※お問合せは上記にお願いします(初回相談無料) |